有終の染色
学校の思い出は、どこを切り取っても濁っている。ただし中学の後半に対する感覚だけは真っ白なままなのだ。ほとんど登校しなかったのだから当然であるが、その大胆な余白によって、ほんの些細な出来事であっても極めて強調されている。
僕は典型的にいじめられてきた。子どもにクレヨンで魚を描かせると、左向きで丸く太ったものを青く表すが、あれは鯵でも鰯でも鮪でもなく、名もなきサカナでしかない。僕が受けた「いじめ」は、凡そそういう調子であった。誰もが想定できるような虐げを粗方受けたためか、いじめという記号に対する手触りが散らばっていく。どこか当事者意識が欠けた猪口才としての幼少期を過ごし、無視されているのか、こちらが話したくないだけなのかを積極的に誤解しようと努めていた。真っ当に傷つくのを避け、青臭く知性や才能を過信する。弱い自分で居たくなくて、血が滲んだ肌や壊れた文房具を隠し続けた。それは傷心の負債となって、いつしか膨れ上がり、思春期になって爆発する。社会性を軽視する自己欺瞞の限界だった。
小学生の頃から深海に沈み込むように布団に潜り、居間に流れる朝の情報番組を遮断しようと試みることはあった。都合のよいことに登校前だけは、いつも吐き気や腹痛がするのだ。それに耐えきれないときが月に数回あった。トイレと布団を何往復していようが、欠席の連絡を入れる母の声がすれば、徐々に治ってしまって情けない。昼間まで心臓が弱い身体のせいにして寝ておいた。潜水すると思考はより巡り、罪悪感を材料に自己否定の連鎖を形作る。神秘的な深海だろうとクレヨンのサカナで汚れるし、カーテンの隙間から射す陽が寝室にいる不調和を指摘するのも苦しかった。
それでも不登校と呼ぶのか呼ばないのか微妙な出席日数を保っていたのは、成績こそが僕のアイデンティティだと信じていたからに他ならない。僕をいじめる奴らとは比べ物にならないテストの点を取り続けることで、コミュニティにおける立ち位置の違いを実感し、小人の罵詈讒謗など無効化できると考えていた。逆に逃げるように家に籠ってしまうのは、彼らの悪意に屈することであって、自分の能力が役立たないと告白する自殺行為だと決めつけた。
ところが、中二になるとそうも言っていられなくなった。いじめは益々エスカレートして、手足の骨を折る大怪我をしたのだ。つまり、いじめられていることが明るみに出る。母だって、悲嘆に暮れ、憐憫を垂れ、学校や加害者には怒りをぶつけた。僕にはもちろん苦痛だった。自分の弱点を論われているとしか感じられず、無理に歯牙にも掛けない態度を取る。しかし、怪我は痛いし、会って話すかと問われると簡単に過呼吸になった。深海で起こした爆発が津波となって押し寄せ、身体には緊急避難命令が出されていたらしい。
むしろ不登校を選ぶことを勧められるようになって、しばらく通院にしか外出しない日々を送った。母から気晴らしにどこかへ行こうと誘われても、太陽の下を堂々と歩くことは許されない気がして、ひたすら深海に潜ってしまう。記憶も不明瞭な数ヶ月を過ごしたが、登校を退けるのに慣れ、遂に怪我まで回復してくると、あっさり体は軽くなった。学校での人間関係という瑣末なものを、強いストレスとして抱えてしまう幼さの証拠が示されたようで、あまり面白くはない。自宅でも変わらず神経衰弱を拗らせている方が望ましいのだが、日毎に落ち着きを取り戻す世界の優しさの前では、素直にさえなれた。
成績よりは本質的な知性にアイデンティティを求めて、カリキュラムに囚われない学習や読書に没頭できるようにもなった。眠れるし、食べられるし、笑える。何年も縛り付けていた自我が唐突に解放されて、一気に成長を取り戻していく手応えがあった。心の傷が全快したような感覚まであったが、調子に乗って朝に制服を着てみようとすると、振戦と悪心に苛まれ、あっという間に血の気が引いた。驚いた。僕は心の澱を押しやって、切り離していただけなのだ。さっぱり洗浄できたわけではない。けれども、あえて克服したいとも思えなかった。もう戻りたくない。不登校の方がずっと自分のためになる。そう言い聞かせた。
勉学はよいとしても、どうしても交際は不足する。インターネットで見知らぬ人と繋がれど、不思議な隔たりを感じて、やはり同年代の子どもと会って話す必要はあるのだと知った。とはいえ、クラスメイトらは絶対に避けたい。不登校について是非を問われることも免れたい。しかし、自身の内実を隠して、あるいは否定したまま、人と関わることは困難を極める。判っていても踏ん切りは付かない。そんな軽い悩みをいつも通り霞ませていた夏休み、来訪があった。
「一緒に宿題やろうと思ってさ、お前の力を借りに来た。」
小学校からの友人だった。僕とは別の中学校に通っている。会う頻度はかなり減っていたが、たまにするメッセージのやり取りだけで、薄い関係を保ってきた。一年生の頃は他愛もないやり取りに意味を見出せなかったが、不登校になって余暇が増えると、こちらは少しずつ長文を送るようになる。ほとんど無意識に、学校に行っていないことや事の経緯について、そこまで訊かれてもいないのに話していた。多分、画面越しだからこそ言えたのだろう。一人称視点では人生の全部を揺るがすドラマであったから、出鱈目なデッサンのサカナでも、人に語ることは蠱惑的なのである。悪く言えば、彼をモルモットにした。友人であったにしたところで、自己満足の演劇に付き合わされた場合、僕なら適当に躱す。そんな非情な人間と違って、彼は真剣に話を聞くばかりか、わざわざ電車にまで乗って我が家を訪れたのだ。容姿も端麗だった。
実際にはさほど困ってもいない平行四辺形に関する問題を、腑に落ちないふりをして僕に尋ねた。好い気になって解説してみせると、彼は気持ちのよい相槌を打つ。しばらくして「元気そうでよかった。」と洩らす顔はしかつめらしく、とても直視できなかったが、気立てのよさには惚れ惚れした。端的に言えば、ありがたかった。ありがたさに感動することは不恰好で言えはしないが、今にも涙が溢れそうで上手く話せなかったため、トイレの回数は多かった。
それからというもの、彼は度々我が家を訪れるようになった。彼に会うために身だしなみを整え、以前よりは人間らしい見た目にもなる。僕が吃って話すのも、偏執的に拘泥るのも、クラスメイトと違って好奇の眼差しを向けないし、長袖をやめて寛いで居られた。母が仕事に出て、二人きりになる時間もあったが、それも構わない。遊戯も猥談も内容は取るに足りないが、一人前に億劫がれることに救われた。
ある日、彼が台所で真鯵の干物を焼いていた。頂き物があったから、よければ二人でおやつにでも食べてくれと、出掛ける前の母が言ったのだ。上等な品であって、彼は愛想よく喜んでいたけれど、本当に焼き出すとは思わなかった。僕は火を使うのもままならないため、彼に任せることになると母だって判っているのに、なんてことを言い出すのだ。他人の家で干物を焼いた経験を持つ中学生がどこに居ようか。それほどまでに我が家に馴染んでくれているのは喜ばしいことだが、申し訳なさも募る。
あまりの重さに盛り付ける際、返し方を失敗してしまったらしい。皮の方が上を向いて右向きになって食卓に出される。一度は謝られたものの、中学生男子としては特に気にならない。一匹の真鯵を前にして、並んで座って二人で突く。すると、黄金色の脂が波打つように押し寄せ、矢羽型の身は弾けつつ解けた。箸でガリガリと皮を裁つ音が、香ばしさを尤もらしくして、複雑に嗅覚を刺激する。美味い美味いと干物に対してとは思えぬ勢いで喰らい付く、彼の清々しい顔がよかった。僕も倣ってドカドカ食べる。ここまで焼き魚を乱雑に食べたことはない。
食い荒らされたサカナを片付け、彼はシンクに向かう。「焼いてくれたのだから洗い物は僕がやる。」との宣言が遅れてしまい「ご馳走になったのは俺の方だから。」と、さっぱり笑って既にスポンジを泡立てていた。僕は火さえ使えないのに、彼は家事に大変慣れている。父子家庭で自分でやることが多いからだと聞いたが、僕のところも親子二人暮らしであるから、その理由付けはやめておいて欲しい。
洗い物をしてくれる彼の後ろで、手持ち無沙汰に突っ立って「要領悪くて、役立たなくて、きっと僕はろくな大人にならないね。」と冗談めいて自己卑下する。否定するしかない面倒なことを言った。そういうところがいけないと、頭のなかでもう一段の叱責をする。決まりきった手続的な会話はつまらないが、彼の返答は単純に僕の言葉を斥けるだけではなかった。
「子どもで居るのが合わないだけだよ。第一、真っ当な大人になんかなりたくなさそうに変人やってるくせに、何言ってんだ。そのヘンを突き詰めたらさ、多分すげー面白い。俺はお前のこと信じてるから、洗い物なんてくだらないことはさせない。」
顔を合わせていなかったから、そんな会話ができたのだろう。深海に光が差し込んだと見えた。棘を均そうとすること自体が、馴染めない自分を際立たせる。それなら一層尖ってみせろと活を入れられた。同級生を馬鹿にするだけして、内心では同化したがっているなんて不誠実にもほどがある。徹底的に違いを見つめて、学校に行けない自分も侮蔑した上で、初めて本当に自分の価値が洗い出される気がする。もとより知っていた価値に収束したとしてもだ。欺瞞を許さない猜疑心に満ち溢れた眼差しを潜り抜けた価値なら、きっと信じられる。颯爽と現れた彼を信じることが、自分自身を信じることだ。
卒業式にも行きたくはなかったが、少し胃を痛めながらなんとか出席した。みんなは僕にない思い出を語り合うことに必死で、いじめのことなど思い出したくなさそうだ。僕は透明人間で居られる。輪に入りたいという欲求もないし、不登校を決めた頃より頭も心も成長している。適切に感じられる隔たりは、自信から生じた防護壁だ。
卒業アルバムを貰って、名残惜しそうに挨拶を交わすなか、アルバムに空いた見開きのスペースへ友人同士で寄せ書きをし合っていた。荷物をまとめて帰路を急ごう。その和気藹々とした空間で孤立しているのも辛いし、手違いで空気に圧されて無理やり入れられても不服だ。捻れたものは、捻れたままでよい。僕にも明日には彼と会う予定がある。
インターフォンを押す。笑顔で出迎えられて、さっさと彼の部屋まで行った。卒業アルバムを見せ合えば、話題の種になるかもしれないと持ってきたが、ほとんど自分が映っていないものを見せるのは、気不味い思いをさせるのでないかと逡巡する。その戸惑いに気づいたのか、彼はバッグの膨らみを指摘して、卒業アルバムを持ってきたなら見せてと言ってくれた。
初めに見たのは卒業文集だった。写真よりも僕のことが詳らかに表れると知っているのかもしれない。「先生は学級の空気を大切にしてくれていた」という表現に皮肉が効いていると一通り笑い、パラパラ捲ると真っ白の見開きが見つかった。「想い出のページ」という見出しを確認して、一瞬だけ沈黙する。彼は突然立ち上がり、油性ペンを持ってきた。
「想い出が真っ白なんてことないだろ。俺が全部埋めてやるよ。」
気障な振る舞いも慣れていたのに、その台詞には目頭を熱くされた。汚い字で白いページが埋まっていく。僕の青春のすべてが色鮮やかに書き表されていくのだ。お返しに彼の卒業アルバムにも何か書き込もうとする。しかし、そのページにはびっしり寄せ書きがされていた。僅かに寂しい思いがしたが、隅の方に「ありがとう」とだけ畏まった字で書いた。僕らは単純な青さのなかを泳いでいるらしい。
その日は最後に、入学式での待ち合わせ場所を確認した。
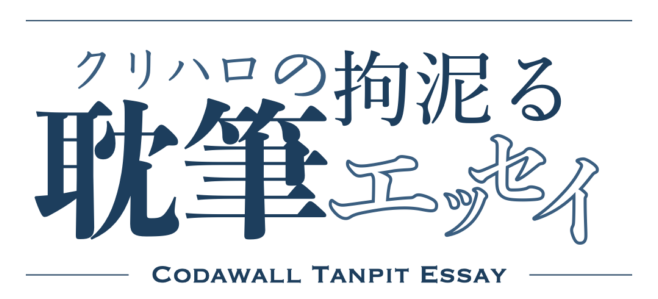

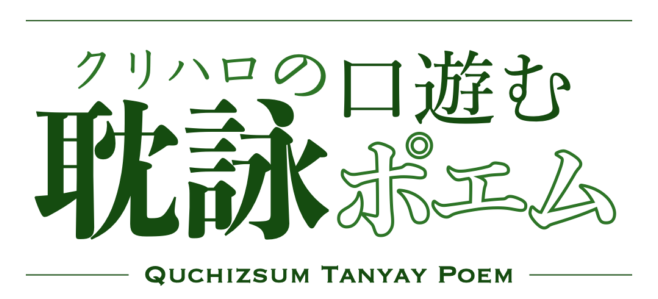
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
感想などはTwitterで受け付けております。#樅木霊



